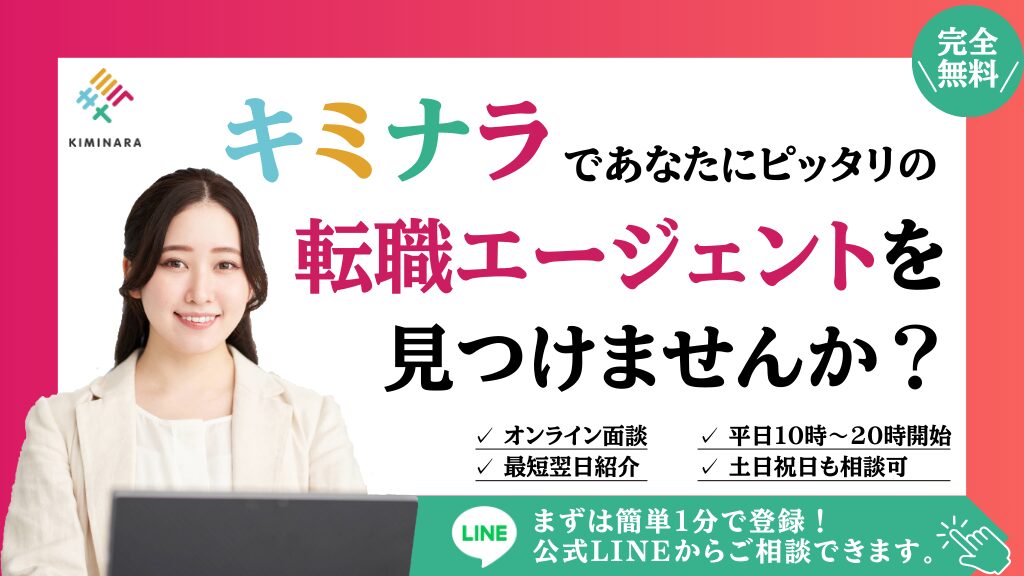会社が辞めさせてくれない時の対処法と転職成功のステップ

「会社を辞めたいのに、辞めさせてくれない…」
そんな悩みを抱えている20代の方は、
意外と多いのではないでしょうか?
法律では、
労働者は2週間前に退職の意思を伝えれば、会社を辞めることができます。
しかし実際には、
会社から引き止められたり、退職を拒否されたりするケースもあるようです。
今回は、会社が辞めさせてくれない時の対処法や円満に退職するためのステップ、そして転職を成功させるためのポイントをご紹介します。
労働者には辞める権利がある
「会社を辞めたい…でも、上司に言い出せない…」
「辞めたいと言ったら、引き止められそうで怖い…」
そんな風に感じていませんか?
もしかしたら、会社や上司との関係性が良好でなかったり、
退職することで迷惑をかけてしまうのではないかと不安に思っていたりするのかもしれません。
あるいは、退職後の生活やキャリアについて、漠然とした不安を抱えているのかもしれません。
ですが、安心して下さい。
労働基準法第16条には
「期間の定めのない雇用契約については、労働者は2週間前に申し出ることにより、雇用契約を解約することができる」
厚生労働省
と明記されています。
つまり、正社員や契約社員として働いている場合、
2週間前に退職の意思を伝えれば会社を辞める権利があるのです。
会社をが辞めさせてくれない理由とは
法律で認められた退職の権利があるにもかかわらず、会社が辞めさせてくれないケースがあります。
一体、なぜ会社は辞めさせてくれないのでしょうか?
その背景には、様々な理由が考えられます。
【離職率をあげたくない】
会社にとって、従業員の離職は大きな損失です。
後任者の採用や育成には
時間やコストがかかります。
新たに人材を採用する場合、
求人広告の掲載費用や面接にかかる人件費、採用担当者の時間など様々なコストが発生します。
また、採用した人材がすぐに辞めてしまうと、これらのコストが無駄になってしまうだけでなく、業務の停滞や他の従業員の負担増加にもつながる可能性があります。
さらに、離職率が高いと企業イメージが悪化し、優秀な人材を獲得するのが難しくなる可能性もあります。
企業イメージは、
企業のブランド価値や顧客からの信頼度にも影響を与えるため非常に重要な要素です。
離職率が高い企業は、
「労働環境が悪い」
「従業員を大切にしない」
といったネガティブなイメージを持たれやすく、優秀な人材から敬遠されてしまう可能性があります。
そのため、会社側は従業員の離職を防ぐために、様々な方法で引き止めようとするケースがあります。
例えば、退職を申し出た従業員に対して、昇給や昇進、配置転換などを提案したり、退職理由を詳しくヒアリングして、改善できる点があれば対応したりするなど引き止め工作を行う企業も少なくありません。
【繁忙期で人がいなくなると困る】
繁忙期など人手不足の時期に退職されると、業務に支障をきたす可能性があります。
特に、人材の補充が難しい状況や専門的な知識やスキルが必要な業務を担当している従業員が退職する場合、その影響は大きくなります。
人材不足が深刻化すると、
残業時間の増加や従業員の業務負担の増加に繋がり、従業員のモチベーション低下やさらなる離職を招く可能性もあります。
また、顧客対応や納期の遅延など顧客や取引先に迷惑をかけてしまう可能性もあります。
そのため、会社側は繁忙期が過ぎるまで退職を待ってほしいと考えるケースがあります。
【上司自身が評価を気にしているケースもある】
上司の中には、自分の評価を気にして、部下の退職を阻止しようとする人もいます。
部下が辞めてしまうということは、上司のリーダーシップ不足やマネジメント能力の不足を露呈してしまう可能性があります。
また、チームや部署の目標達成に影響が出たり、他のチームメンバーのモチベーションが低下したりする可能性もあります。
これらの要因が上司の評価に悪影響を及ぼす可能性があるため、上司は部下の退職を引き止めようとするケースがあります。
中には、部下との個人的な関係を重視しすぎてしまい、退職を感情的に引き止めてしまう上司もいるかもしれません。
しかし、上司の評価のために従業員のキャリアや人生を犠牲にすることは許されることではありません。
従業員は、自分の意思で自分のキャリアプランに基づいて、転職する権利があります。

【状況別】退職できないときの対処法
会社が辞めさせてくれないという事態には、様々な状況があります。
ここでは、状況別に適切な対処法を解説していきます。
【退職届を受け取ってもらえない場合】
退職届を提出しても、上司や人事部が受け取り拒否してしまうケースがあります。
このような場合は、内容証明郵便で退職届を送付する必要があるでしょう。
内容証明郵便とは、
いつ、誰が、誰に、どのような内容の文書を送ったのかを郵便局が証明してくれるサービスです。
内容証明郵便で退職届を送付することで、会社側に退職の意思を明確に伝えることができます。
また、退職届を提出する際には、コピーを保管しておきましょう。
【退職日までが長い場合】
会社によっては、就業規則などで退職の申し出から退職日までの期間を定めている場合があります。
しかし、法律では2週間前に退職の意思を伝えれば、会社を辞めることができます。
そのため、会社が指定した退職日よりも早く辞めたい場合は、上司や人事部に相談し、退職日を交渉してみましょう。
その際、労働基準法第16条で定められた退職の権利について言及することも有効です。
【損害賠償・懲戒解雇などの脅しを受けている場合】
中には、退職を申し出た従業員に対して、損害賠償を請求したり、懲戒解雇を言い渡したりする会社もあるようです。
しかし、正当な理由なく損害賠償を請求したり、懲戒解雇をしたりすることは、法律で禁止されています。
もし、会社から不当な扱いを受けた場合は、労働基準監督署や弁護士に相談しましょう。
【有給消化を認めてくれない場合】
法律では、労働者には一定期間の勤務に対して、有給休暇を取得する権利が認められています。
また、退職時に残っている給与は、会社に支払う義務があります。
もし、会社が有給休暇の取得や残りの給与の支払いを拒否する場合は、労働基準監督署に相談しましょう。
【年収交渉をしてきた場合】
退職を申し出た従業員に対して、年収交渉をしてくる会社もあります。
これは、従業員を引き止めるための一つの手段です。
もし、年収交渉に応じる場合は、条件面をよく確認し納得した上で契約を結びましょう。
ただし、年収交渉に応じたとしても
将来的なキャリアプランを考えた上で、転職するのか、残留するのかを判断する必要があります。
それでも!辞められないときはどうすればいい?
上記の対処法を試しても、会社が辞めさせてくれない場合は、どうすれば良いのでしょうか?
ここでは、さらに具体的な方法を3つご紹介します。
【退職の意思を直属の上司にはっきりと伝える】
まずは、直属の上司に退職の意思を明確に伝えましょう。
その際、退職理由を具体的に説明することで上司の理解を得やすくなります。
また、退職の意思が固いことをはっきりと伝えることも重要です。
【さらに上の上司・人事部へ】
直属の上司に相談しても、状況が改善されない場合は、さらに上の上司や人事部に相談してみましょう。
直属の上司よりもより客観的な立場で話を聞いてくれる可能性があります。
【労働基準監督署に相談する】
それでも会社が辞めさせてくれない場合は、労働基準監督署に相談してみましょう。
労働基準監督署は、労働条件や労働環境に関する相談を受け付けており、必要があれば、会社に対して指導を行ってくれます。
相談方法は、電話、メール、または直接訪問のいずれかを選べます。
連絡先や相談窓口の詳細は、厚生労働省のウェブサイトで確認できます。
仕事を辞めるまでにやるのが望ましいこと4選
円満に退社するためには、事前にしっかりと準備しておくことが大切です。
ここでは、退職前にやっておくべきことを4つご紹介します。
【在職中に引き継ぎ】
退職前に、後任者への引き継ぎをしっかりと行いましょう。
引き継ぎが不十分だと
会社に迷惑をかけてしまう可能性があります。
また、引き継ぎ資料を作成する際は、後任者が理解しやすいように分かりやすく丁寧に作成することが重要です。
【チェックリストを作成】
退職時には、会社から貸与されている物や会社から受け取る書類があります。
事前にチェックリストを作成しておくことで、退職手続きをスムーズに進めることができます。
会社から貸与されている物としては、社員証、パソコン、携帯電話などがあります。
また、会社から受け取る書類としては、離職票、源泉徴収票などがあります。
【社会保険や税金の手続きについて調べておく】
退職後は、社会保険や税金の手続きが必要です。
事前に手続きについて調べておくことで、手続き漏れを防ぐことができます。
社会保険の手続きとしては、
健康保険の資格喪失手続き、厚生年金被保険者であった場合は年金事務所で資格喪失の届出が必要です。
また、税金の手続きとしては、住民税の変更手続きなどがあります。
【失業保険の申請方法を把握しておく】
退職後、再就職を希望する場合は、雇用保険の基本手当を申請することができます。
雇用保険の基本手当は、退職後、一定の条件を満たすことで支給される給付金です。
事前に申請方法を把握しておくことで、スムーズに手続きを進めることができます。
会社を辞められない・辞めさせてもらえない場合の相談先4選
会社を辞めたいのに辞めさせてくれない場合は、一人で悩まずに、専門機関に相談してみましょう。
ここでは、相談できる機関を4つご紹介します。
【退職手続きのアドバイスがほしい方】
労働局や労働基準監督署は、労働条件や労働環境に関する相談を受け付けています。
退職手続きに関するアドバイスや会社とのトラブル解決のサポートを受けることができます。
労働基準監督署は、各都道府県に設置されている国の機関で、労働基準法をはじめとする労働関係法令の遵守を監督し、労働条件の改善を図ることを目的としています。
労働基準監督署では、賃金不払い、残業代未払い、解雇、ハラスメントなど、様々な労働問題に関する相談を受け付けています。
相談方法は、電話、面談、メールなど、様々な方法があります。
相談内容に応じて、担当者が適切なアドバイスや指導を行ってくれます。
また、必要に応じて会社への調査や行政指導なども行います。
労働基準監督署への相談は無料です。
相談内容に関する秘密は厳守されますので、安心して相談することができます。
【退職代行サービス|退職手続きを代わってほしい方】
退職代行サービスは、退職の意思を会社に伝えてくれたり、退職手続きを代行してくれたりするサービスです。
会社と直接連絡を取りたくない方や退職手続きに時間をかけたくない方におすすめです。
退職代行サービスは、近年利用者が増加しているサービスです。
退職代行サービスを利用するメリットは、以下の点が挙げられます。
- 会社と直接連絡を取らなくて済む
- 退職手続きをスムーズに進めることができる
- 専門家によるアドバイスやサポートを受けることができる
- 精神的な負担を軽減することができる
退職代行サービスの利用料金は、サービス内容や業者によって異なりますが、一般的には数万円程度です。
退職代行サービスを利用する際は、信頼できる業者を選ぶことが重要です。
業者の評判や実績、料金体系などを比較検討し、自分に合った業者を選びましょう。
【弁護士|退職手続きだけでなく労働問題全般を解決してほしい方】
弁護士は、法律の専門家です。
退職手続きに関するアドバイスだけでなく、会社とのトラブル解決や損害賠償請求などの法的対応をサポートしてくれます。
弁護士に相談するメリットは、以下の点が挙げられます。
- 専門的な知識に基づいたアドバイスを受けることができる
- 法的対応が必要な場合に、適切なサポートを受けることができる
- 精神的な負担を軽減することができる
弁護士への相談は、有料の場合が多いです。
相談料や着手金、報酬金など、費用体系は弁護士や法律事務所によって異なります。
弁護士に相談する際は、事前に費用について確認しておきましょう。
【転職エージェント|自分に合った転職先を探したい方】
転職エージェントは、転職のプロフェッショナルです。
自分に合った転職先を紹介してくれたり、転職活動のアドバイスをしてくれたりします。
転職エージェントは、求人企業と求職者の仲介役となり、転職活動をサポートするサービスです。
転職エージェントを利用するメリットは、以下の点が挙げられます。
- 非公開求人を含め、多くの求人情報の中から自分に合った求人を紹介してもらえる
- 応募書類の作成や面接対策など、転職活動全般のアドバイスを受けることができる
- 企業との給与交渉や入社条件の交渉などを代行してもらえる
- 転職活動に関する不安や悩みを相談できる
転職エージェントのサービスは、求職者にとって無料です。
転職エージェントは、求人企業から手数料を受け取って運営しているため、求職者は無料でサービスを利用することができます。
転職エージェントを利用する際は、複数のエージェントに登録し自分に合ったエージェントを選ぶことが重要です。
困ったらオススメ!キミナラで転職!
「会社を辞めたいけど、辞めさせてくれない…」
「転職したいけど、何から始めればいいか分からない…」
そんな方は、キミナラのキャリアカウンセリングをご利用ください。
キミナラは、20代の転職活動をサポートするサービスです。
経験豊富なキャリアコンサルタントが、あなたの悩みや不安を丁寧にヒアリングし、最適な転職活動の進め方をアドバイスします。
転職活動がスムーズに進むよう、
あなたにぴったりの転職エージェントを見つけるお手伝いもしています。
数多くの転職エージェントの中から、あなたの希望や条件に合った信頼できるエージェントを厳選し、ご紹介します。
LINEでの相談も受け付けており、転職活動に関する疑問や不安をいつでも解消できます。
サービスは完全無料でご利用いただけますので、お気軽にカウンセリングにお申し込みください。
まとめ
今回は
会社が辞めさせてくれない時の対処法、円満に退職するためのステップ転職を成功させるためのポイントをご紹介しました。
法律では、労働者は2週間前に退職の意思を伝えれば、会社を辞めることができます。
もし、会社が辞めさせてくれない場合は、今回ご紹介した対処法を参考に適切な対応をとりましょう。
円満に退職するためには、後任者への引き継ぎをしっかりと行い、会社から貸与されている物の返却や社会保険、税金などの手続きを忘れずに行うことが重要です。
転職は、新しいキャリアをスタートさせるための大きなチャンスです。
事前にしっかりと準備を行い、自信を持って転職活動に臨みましょう。
もし、転職活動に不安や悩みがある場合は、キミナラのキャリアカウンセリングをご利用ください。
経験豊富なキャリアコンサルタントが、あなたの転職活動を全力でサポートします。

キミナラ編集室。1997年福岡県博多市生まれ。東京都在住。大手人材派遣会社で4年間経験。
海外事業部に所属。主に海外企業との渉外業務を担当し、グローバルなビジネス感覚を身につける。
現在はキミナラ編集部で、データ分析や20代の転職事情に関する記事を担当しています。
好きな食べ物: お寿司
趣味は 2か月に一回の海外旅行や毎週土曜日のヨガです。