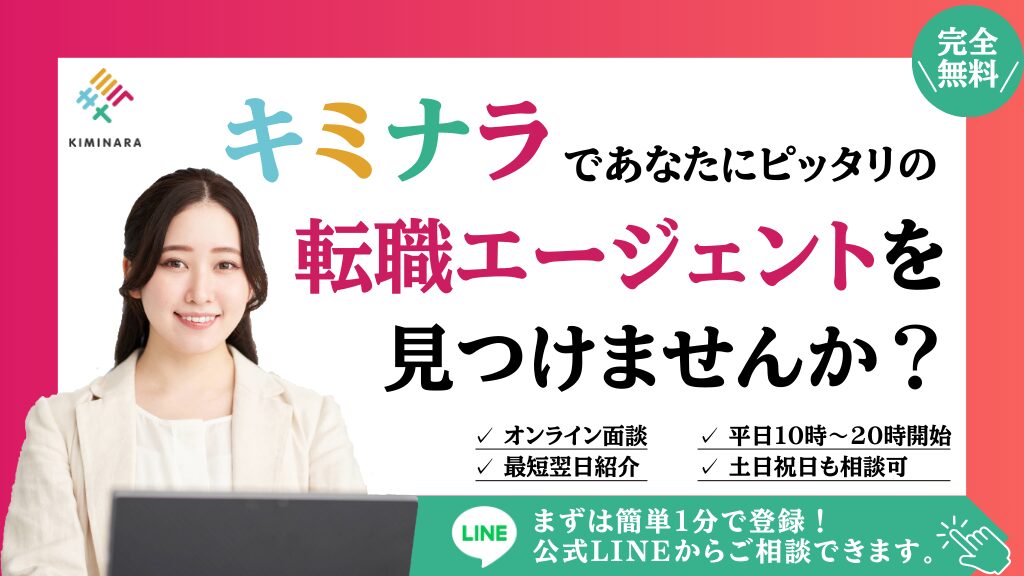仕事ができない人の特徴と原因|改善策を徹底解説

「仕事ができない」と感じ、悩んでいませんか?
この記事では、仕事ができない人の特徴や原因を分析し、具体的な改善策、周りの人への接し方を解説していきます。
仕事で抱える悩みを解決し、自信を持って活躍できるヒントになるはずです。
ぜひ、最後まで読んでみてください。
仕事ができない人の特徴:
「仕事ができない人」には、共通する特徴があります。
周囲を見渡してみると、思い当たる人がいるかもしれません。
■優先順位がつけられない
仕事ができない人は、複数のタスクを抱えたときに、どれから取り組むべきか、優先順位をつけるのが苦手です。
そのため、締め切り間際に慌ててしまったり、重要なタスクが後回しになってしまったりします。
例えば、AさんとBさんの2人がいるとします。
Aさんは、締め切りが近いタスクを優先的に取り組み、余裕を持って仕事を終わらせることができます。
一方、Bさんは、締め切りが近いタスクよりも、簡単なタスクから手を付けてしまい、結局締め切りに間に合わなくなってしまうことがあります。
このように、優先順位をつけられない人は、時間管理が苦手で、非効率な働き方をしてしまう傾向があります。
では、時間管理能力が低い人は、どのような特徴があるのでしょうか?
次で詳しく見ていきましょう。
■時間管理が苦手
仕事ができない人は、時間管理が苦手で、時間を無駄にしてしまうことが多いです。
会議に遅刻したり、ダラダラと残業したり、非効率な働き方をしてしまいます。
例えば、CさんとDさんの2人がいるとします。
Cさんは、会議の開始時刻に間に合うように、事前に資料を準備し、時間配分を考えて会議に臨みます。
一方、Dさんは、会議の直前に資料を準備し始め、時間配分も考えずに会議に臨みます。
そのため、Dさんは会議に遅刻したり、会議中に資料が足りなくなって慌ててしまったりすることがあります。
このように、時間管理が苦手な人は、時間にルーズで、周囲に迷惑をかけてしまうことがあります。
■コミュニケーション不足
仕事ができない人は、コミュニケーション不足に陥りがちです。
報連相を怠ったり、質問や相談をせずに一人で抱え込んでしまったり、周囲との連携がうまく取れません。
例えば、EさんとFさんの2人がいるとします。
Eさんは、上司や同僚に進捗状況を報告したり、困ったことがあれば相談したりすることで、スムーズに仕事を進めることができます。
一方、Fさんは、上司や同僚に報告や相談をせずに、一人で仕事を進めてしまい、ミスやトラブルが発生することがあります。
このように、コミュニケーション不足は、仕事上のミスやトラブルに繋がりやすいため、注意が必要です。
では、責任感がない人は、どのような行動をとってしまうのでしょうか?
次で解説していきます。
■責任感がない
仕事ができない人は、責任感がないため、ミスをしても言い訳をしたり、人のせいにしたりします。
また、自分の仕事に責任を持たず、周囲に迷惑をかけてしまうことも少なくありません。
例えば、GさんとHさんの2人がいるとします。
Gさんは、ミスをしてしまったときは、素直に自分の非を認め、改善策を考えます。
一方、Hさんは、ミスをしてしまったときは、言い訳をしたり、人のせいにしたりします。
また、Hさんは、自分の仕事に責任を持たず、周囲に迷惑をかけてしまうことも少なくありません。
このように、責任感がない人は、周囲からの信頼を失い、孤立してしまう可能性があります。
では、仕事ができないことで、具体的にどのような問題が発生するのでしょうか?
次の章で詳しく見ていきましょう。
仕事ができないことで生じる問題
仕事ができないことは、あなた自身だけでなく、周囲にも悪影響を及ぼします。
どのような問題が起こりうるのか、具体的に見ていきましょう。
■職場での信頼を失う
仕事ができないと、周囲からの信頼を失ってしまいます。
ミスが多い、締め切りを守れない、責任感がないなどの行動は、周囲の信頼を損ない、孤立してしまう原因になります。
例えば、IさんとJさんの2人がいるとします。
Iさんは、常に締め切りを守り、質の高い仕事をすることで、上司や同僚からの信頼を得ています。
一方、Jさんは、締め切りを守らなかったり、ミスが多いことから、上司や同僚からの信頼を失っています。
このように、職場での信頼を失うと、仕事がしづらくなるだけでなく、精神的なストレスも大きくなってしまいます。
■キャリアアップのチャンスが遠のく
仕事ができないと、昇進や昇給などのキャリアアップのチャンスを逃してしまう可能性があります。
企業は、能力や成果を評価して昇進や昇給を決定します。
仕事ができない状態では、評価が低くなり、キャリアアップが難しくなります。
例えば、KさんとLさんの2人がいるとします。
Kさんは、高い能力と実績を評価され、昇進することができました。
一方、Lさんは、仕事ができないことから評価が低く、昇進のチャンスを逃してしまいました。
このように、キャリアアップを望むのであれば、仕事ができるよう努力することが重要です。
■ストレスが増える
仕事ができない状態が続くと、ストレスが増えてしまいます。
ミスを繰り返すことへの不安、周囲からのプレッシャー、自己嫌悪など、様々なストレス要因が積み重なり、精神的な負担が大きくなります。
例えば、MさんとNさんの2人がいるとします。
Mさんは、仕事ができないことから、常に不安やプレッシャーを感じ、ストレスを溜め込んでいます。
一方、Nさんは、仕事ができることから、自信を持って仕事に取り組むことができ、ストレスをあまり感じていません。
このように、ストレスを減らし、心身ともに健康な状態で働くためには、仕事ができるよう努力することが大切です。
では、なぜ人は仕事ができない状態に陥ってしまうのでしょうか?
次の章では、仕事ができない原因について詳しく解説していきます。
仕事ができない原因
仕事ができない人には、様々な原因が考えられます。
ここでは、主な原因を3つのカテゴリーに分けて解説します。
■能力不足:
知識や経験が不足していると、仕事に対応できないことがあります。
また、専門的なスキルが求められる仕事で、そのスキルを習得していない場合も、仕事ができないと評価されてしまう可能性があります。
例えば、OさんとPさんの2人がいるとします。
Oさんは、営業の仕事に必要な知識や経験が豊富で、顧客との商談をスムーズに進めることができます。
一方、Pさんは、営業の仕事に必要な知識や経験が不足しているため、顧客との商談でうまく対応することができません。
このように、能力不足は、仕事のパフォーマンスに大きな影響を与えます。
では、スキル不足が原因で仕事ができない場合は、どうすれば良いのでしょうか?
次で詳しく見ていきましょう。
■スキル不足:
コミュニケーション能力、問題解決能力、時間管理能力など、仕事に必要なスキルが不足していると、仕事ができない状態に陥りやすくなります。
これらのスキルは、仕事を進める上で非常に重要であり、不足していると、様々な場面で支障をきたす可能性があります。
例えば、QさんとRさんの2人がいるとします。
Qさんは、高いコミュニケーション能力を持ち、上司や同僚と良好な関係を築くことができます。
一方、Rさんは、コミュニケーション能力が低いため、上司や同僚とのコミュニケーションに苦労し、仕事がうまく進まないことがあります。
このように、スキル不足は、仕事上の様々な場面で支障をきたす可能性があります。
■メンタル的な要因:
ストレス、不安、うつ病などのメンタル的な問題は、仕事のパフォーマンスに大きな影響を与えます。
集中力の低下、モチベーションの低下、ミスが増えるなど、仕事ができない状態に繋がる可能性があります。
例えば、SさんとTさんの2人がいるとします。
Sさんは、仕事で大きなストレスを抱えており、集中力やモチベーションが低下し、ミスが増えてしまっています。
一方、Tさんは、ストレスをうまく解消できているため、集中力やモチベーションを高く保ち、質の高い仕事をすることができています。
このように、メンタル的な問題は、仕事のパフォーマンスに大きな影響を与えるため、注意が必要です。
では、仕事ができない状態から抜け出すにはどうすれば良いのでしょうか?
次の章では、具体的な改善策を紹介していきます。
仕事ができない状態から脱却するための改善策
仕事ができない状態から脱却するためには、具体的な行動を起こす必要があります。
ここでは、効果的な改善策を5つ紹介します。
■自己分析:
まずは、自分自身を理解することが重要です。
自分の強みや弱み、得意なことや苦手なことを把握することで、改善すべきポイントが見えてきます。
自己分析には、様々な方法があります。
例えば、自分の過去の経験を振り返ったり、周囲の人から意見を聞いたり、性格診断テストを受けてみたりするのも良いでしょう。
重要なのは、自分自身と向き合い、客観的に自分を見つめ直すことです。
■目標設定:
「仕事ができるようになりたい」という漠然とした目標ではなく、具体的な目標を設定しましょう。
例えば、「1ヶ月以内に、資料作成のスキルを向上させる」「3ヶ月以内に、プレゼンで成功する」など、具体的な目標を設定することで、モチベーションを維持しやすくなります。
目標を立てる際には、SMARTの法則を意識すると良いでしょう。
SMARTとは、Specific(具体的)、Measurable(測定可能)、Achievable(達成可能)、Relevant(関連性)、Time-bound(期限)の頭文字をとったものです。
SMARTの法則に基づいた目標設定をすることで、より効果的に目標を達成することができます。
■スキルアップ:
仕事に必要な知識やスキルを身につけるためには、積極的に学ぶ姿勢が重要です。
書籍やインターネットで情報収集したり、研修やセミナーに参加したり、資格取得を目指したり、様々な方法でスキルアップを図りましょう。
スキルアップの方法を選ぶ際には、自分の目標やキャリアプランに合わせて、最適な方法を選ぶようにしましょう。
例えば、将来的に管理職を目指しているのであれば、リーダーシップやマネジメントに関するスキルを身につけるための研修に参加するのが良いでしょう。
■コミュニケーション能力を高める:
コミュニケーション能力は、仕事をする上で欠かせないスキルです。
報連相を徹底し、上司や同僚との情報共有を密にすることで、連携をスムーズにすることができます。
また、積極的に質問することで、疑問点を解消し、誤解を防ぐことができます。
コミュニケーション能力を高めるためには、日頃から意識してコミュニケーションをとるように心がけましょう。
例えば、上司や同僚に話しかける機会を増やしたり、会議やプレゼンで積極的に発言したりするのも良いでしょう。
では、もしあなたの周りの人が仕事ができない場合は、どのように接すれば良いのでしょうか?
次の章で詳しく解説して行きます。
周りの人が仕事ができない場合の接し方
周りの人が仕事ができない場合、どのように接すれば良いのでしょうか?
ここでは、効果的な接し方を4つ紹介します
■冷静に対応する:
周りの人が仕事ができない場合、イライラしたり、怒ってしまったりするかもしれません。
しかし、感情的に接するのではなく、まずは冷静に対応しましょう。
相手の状況を理解しようと努め、なぜ仕事ができないのか、何に困っているのかを把握することが重要です。
例えば、相手が仕事ができない原因が、能力不足ではなく、メンタル的な問題を抱えている場合は、叱責するのではなく、相談に乗ってあげたり、サポートをしてあげたりする方が効果的です。
■具体的に伝える:
仕事ができない人には、具体的な指示を与えることが重要です。
曖昧な指示では、相手は何をすれば良いのか理解できず、混乱してしまう可能性があります。
「この資料を明日までに作成してください」のように、具体的な行動や期日を伝えることで、相手は行動しやすくなります。
また、指示を出す際には、相手の能力や経験を考慮することも重要です。
相手が経験の浅い新人であれば、丁寧に指示をしたり、サポートをしてあげたりする必要があるでしょう。
■サポートする:
仕事ができない人をサポートすることで、成長を促すことができます。
例えば、業務の進め方やコツを教えたり、困っていることがあれば相談に乗ったり、できる範囲でサポートをしてあげましょう。
サポートをする際には、相手の自主性を尊重することも重要です。
相手に任せっきりにするのではなく、あくまでもサポート役に徹し、相手が自分で考え、行動できるように促しましょう。
■相談する:
周りの人が仕事ができない場合、一人で抱え込まずに、上司や同僚に相談してみましょう。
客観的な意見を聞くことで、新たな解決策が見つかるかもしれません。
また、上司や同僚と協力して対応することで、負担を軽減することができます。
相談する際には、具体的な状況や問題点を整理しておくことが重要です。
そうすることで、上司や同僚も的確なアドバイスをしやすくなります。
まとめ
この記事では、仕事ができない人の特徴、原因、改善策、周りの人への接し方を解説しました。
仕事ができない状態は、決して恥ずべきことではありません。
大切なのは、現状を把握し、改善に向けて行動することです。
自己分析、目標設定、スキルアップ、コミュニケーション能力の向上など、できることから始めてみましょう。
周りの人のサポートも得ながら、仕事ができない状態を脱却し、活躍できる自分を目指しましょう。
キミナラは、キャリアに悩む方に向けて、最適な転職エージェントを紹介するサービスです。
経験豊富なキャリアコンサルタントが、あなたの強みや弱みを分析し、あなたにぴったりの転職エージェントを提案します。
転職を考えている方、自分のキャリアに悩んでいる方は、ぜひキミナラのサービスをご利用ください。

キミナラ編集室。1997年福岡県博多市生まれ。東京都在住。大手人材派遣会社で4年間経験。
海外事業部に所属。主に海外企業との渉外業務を担当し、グローバルなビジネス感覚を身につける。
現在はキミナラ編集部で、データ分析や20代の転職事情に関する記事を担当しています。
好きな食べ物: お寿司
趣味は 2か月に一回の海外旅行や毎週土曜日のヨガです。